19世紀前半(1)
ガストロノミーの誕生
19世紀前半はガストロノミーにとって揺籃期であり、成長期であり、成熟期であり、衰退期でもあった重要な時期です。この半世紀の間に、ガストロノミーはほぼ完結してしまいます。それにはもちろん異論もあるでしょうが、ここからそれを少し詳細に見ていきましょう。そもそも、ガストロノミーという言葉は18世紀までは存在しませんでした。いや、存在はしていたけれどほとんどまったく使われていなかったと言ったほうが正確でしょう。忘却のかなたに埋もれていたこの言葉を歴史の墓場から掘り起こして陽の目を見させたばかりか眩いほどの輝きをも与たのは、ジョセフ・ベルシュー(Joseph Berchoux)でした。新しい世紀が始まったばかりの1801年に彼が書いた1篇の長詩、それがその後のパリの食文化を大きく方向づけるきっかけとなったのです。
タイトルはその名もずばり「ガストロノミー(Gastronomie)」。4歌からなる一連の詩にそれぞれの詳細な注釈がついたこの長詩は、発表されるやあっという間にフランス国内はもとより国外にまで広まりガストロノミーという言葉に新しい生命を吹き込んだのでした。
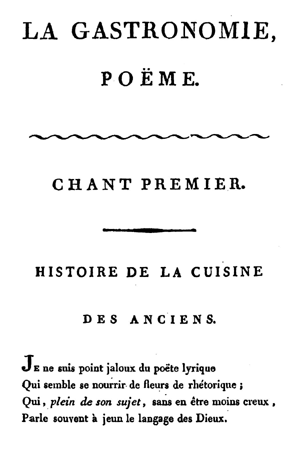
「Gastronomie」の第1歌の冒頭ページ
「消化器」を意味する gastro と「法則」を意味する nomos を組み合わせたギリシャ語の gastronomos はギリシャの古い文献である「食卓の賢人」の中で引用されている書物のタイトルです。「食卓の賢人」は17世紀になってフランス語に翻訳されましたが、その時に gastronomos の訳語として造語されたのが gastronomie でした。この本来は学術用語であった言葉をベルシューは自らの長詩のタイトルとして採用し、新しい意味を与えた上で大いに讃えたのです。その新しい意味とは?
実は意外なことにこの長詩の中でベルシューはガストロノミーという言葉を一度も使っていません。タイトルのみです。そして、そこからベルシューの意図も読み取れるように思えます。すなわち、ベルシューはこの長い詩で語っていることの総体がガストロノミーなのだと暗示しいているのではないでしょうか。であるならば、ガストロノミーの新しい意味もベルシューの詩の中に織り込まれていることになります。
「ガストロノミー」は第1歌の「いにしえの料理の歴史」に始まって、第2歌の「第1の供卓」、第3歌の「第2の供卓」、第4歌の「デザート」と続き、それぞれの末尾に注釈が加えられています。どの詩も食の歓びを謳いあげる内容です。第4歌「デザート」の一節を見てみましょう。
壮麗な建造物に生まれ変わった砂糖
ボンボンの城やビスキュイの宮殿
砂糖漬けのルーブルやバガテルやベルサイユ
サフォやアベラール、ティブールの愛
ガマシュの結婚やヘラクレスの偉業
そして千にものぼるさまざまな主題が
練達の砂糖菓子職人の手によって作られている
この砂糖の驚異を損なうことなかれ
ただ眼を愉しませるために作られたものゆえに
ボンボンの城やビスキュイの宮殿
砂糖漬けのルーブルやバガテルやベルサイユ
サフォやアベラール、ティブールの愛
ガマシュの結婚やヘラクレスの偉業
そして千にものぼるさまざまな主題が
練達の砂糖菓子職人の手によって作られている
この砂糖の驚異を損なうことなかれ
ただ眼を愉しませるために作られたものゆえに
この詩句を読んだだけでガストロノミーという言葉にこめられたベルシューの思いが伝わってきます。
「ガストロノミー」はパリの社交界に一大旋風を巻き起こしました。これによってガストロノミーという言葉そのものが一種の流行語になったのです。なぜ単なるひとつの言葉に過ぎないガストロノミーがそこまでもてはやされたのでしょう?
その背景には18世紀から続いてきた食への関心の高まりがありました。それを象徴するのがパリにおけるレストランの興隆です。
フランス革命直前に誕生したパリの高級レストランは、革命を期に一気にその数を増やし、メオやルガック、ベリー、ロシェ・ド・カンカル、トロワ・フレール・プロバンソーといった人気店を次々と輩出しました。従来の裕福な貴族やブルジョワだけでなく、革命を商機と捉えて成り上がった新興富裕層も、この時代の最先端を行く新しい外食施設にせっせと通い続けたのです。
こうしたレストランの突発的な隆盛はいったいなぜ起こったのでしょうか?
ここで「18世紀以前」の「美食の始まり」の項の最後に記した次の文言をもう一度思い出してみたいと思います。
さしあたっては上記の宴がいずれも裕福な人物によって主催されていることに注目しておきましょう。
この時代、レストランで食事をするのは大変お金がかかりました。セバスチャン・メルシエが「タブロー・ド・パリ(Tableau de Paris, 1788年)」の中で、ポケットに大金の持ち合わせがないのなら、注文をする前に懐勘定をした上で食欲を抑制しなければならない、と嘆いているくらいです。だからレストランに通えるのは金持ちに限られていました。そして金持ちがレストランに通うのは、彼らが皆食通で美味しい料理を愛していたからではありません。“レストランで食事をするのは大金がかかる”というまさにそのこと自体が彼らをレストランに惹きつけたのです。
つまり、レストランに通うのは富裕なものたちにとって自分の富をひけらかす絶好の機会であり、ステータスだったということです。ですから、料理の味が分かろうが分かるまいが、そんなことには関係なく彼らはせっせと高級レストランに通ったのでした。
しかしながら、美味しいものをたらふく食べるというのは、本来は悪徳行為でした。と言うのも、それはキリスト教の教えのひとつである「7つの大罪」に含まれる「大食の罪」そのものだったからです。大喰らいで知られそれを誇ってさえいたルイ14世のような王のもとで、フランスにおける「大食の罪」はさしたる罪とは捉えられていませんでしたが、それでも罪は罪です。
金持ち連中は高級レストランでの食事というパフォーマンスに心惹かれながらも、一方では頭の片隅から罪の意識を追い払うことができずにいました。美味に酔いがらも、どこか後ろめたい気持ちを拭うことができなかったのです。
そんな中途半端な欲望に解決の光を投げかけてくれたのがガストロノミーでした。
ガストロノミーは本来は学術用語です。その言葉をベルシューは詩という形で文学に変身させました。いずれにしても、その言葉から漂ってくるのは高尚な知性の香気です。レストランでの食事に後ろめたさを感じていた金持ち連中は、たちまちこの香気に飛びつきました。レストランで料理を堪能するのは単なる大喰らいではない。ガストロノミーを実践するという知的で気高い行為なのだ。
こうしてガストロノミーという罪の意識を払拭させる魔法の呪文を手に入れた富裕層は、後顧の憂いなくレストランでの浪費に精を出せるようになりました。それと同時にガストロノミーという言葉も富裕な人びとの熱烈な支持のもとあっという間に広まったのです。